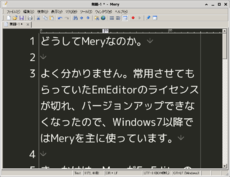2015年02月28日
「白と金」「いや青と黒だ」あなたはどっちに見える? 1枚の写真をめぐりネットで激論
Webのつまらんニュースを読んでいたら、エロ偉い人たちが激論を交わしているそうだ。

結論から言うと、単なるカメラの露出過多。
カメラの標準露出は、18%の反射率の被写体をそのまま再現することが目標だ。だから、真っ黒なものも、真っ白なものも、すべては、全体平均が18%になる灰色を目指して露出調整される。ちなみに、18%の反射率は、人間の肌を基準に考えられた数値らしい。肖像写真や記念写真の用途にはぴったりだから。
分かりにくい人のために、例を少々。
冬の高原を訪れて、雪の美しさに感動した人が、あたり一面の雪景色を記念撮影した。ところが、写真を確認してみると、汚らしい灰色の雪野原だった……orz。手元にカメラがあれば、真っ白なシャツや白いタオルの、白い部分だけを撮影してみればすぐに分かる。
元来、この写真はプラスの補正が必要な逆光の被写体。しかも、カメラの測光機能が、画面の中央部のほとんどを占めている「明度が低い被写体」(暗い青と黒の服)を、標準露出に基づいて無理矢理明るくしてしまったから、灰色っぽくなっただけ。このとき、彩度はいっさい関係ない。
かなりのヲタクで賢い方が、補正した画像をupしている。

どんなに莫迦でもすぐに分かることは、DARKERの服の右側が最も自然な露出になっていること。他は、完全な露出オーバー。

結論から言うと、単なるカメラの露出過多。
カメラの標準露出は、18%の反射率の被写体をそのまま再現することが目標だ。だから、真っ黒なものも、真っ白なものも、すべては、全体平均が18%になる灰色を目指して露出調整される。ちなみに、18%の反射率は、人間の肌を基準に考えられた数値らしい。肖像写真や記念写真の用途にはぴったりだから。
分かりにくい人のために、例を少々。
冬の高原を訪れて、雪の美しさに感動した人が、あたり一面の雪景色を記念撮影した。ところが、写真を確認してみると、汚らしい灰色の雪野原だった……orz。手元にカメラがあれば、真っ白なシャツや白いタオルの、白い部分だけを撮影してみればすぐに分かる。
元来、この写真はプラスの補正が必要な逆光の被写体。しかも、カメラの測光機能が、画面の中央部のほとんどを占めている「明度が低い被写体」(暗い青と黒の服)を、標準露出に基づいて無理矢理明るくしてしまったから、灰色っぽくなっただけ。このとき、彩度はいっさい関係ない。
かなりのヲタクで賢い方が、補正した画像をupしている。

どんなに莫迦でもすぐに分かることは、DARKERの服の右側が最も自然な露出になっていること。他は、完全な露出オーバー。
2014年07月27日
『霞町物語』 浅田次郎より
『霞町物語』 浅田次郎

再再度、読了。
1951年生まれの作者の青春時代が反映された作品。実体験にしろ、聞きかじりであったにしろ、生粋の江戸っ子で、ある程度お金持ちでなければその存在さえ知らないことも多々。勉強になりますた……orz。
さすがは、直木賞作家。「すばらしい言い回し!」「かっこいい伏線!」と、うめいたことが多々。
印象に残ったことばを少々、
「霞町物語」……「ごきげんよう」・孔雀の羽のいろをしたドレス
「夕暮れ隧道」……波間に漂うクラゲのようになった女・「そっくりね、今日の私たち」
「青い火花」……「おめえは、やさしさが足んねえ。」・幸福な子供
「雛の花」……セピア色・「おおなりこま」
「卒業写真」……スチール写真・幸福な子供
反面、カメラや写真に関しては、「これ、きっと勘違い」と時代考証してみたり、「それって、ど素人の考え」と毒ついてみたり。
浅田次郎の実家は、写真機材の卸商だったとかカメラ屋だったとかいうWebデータが実在するところから、カメラや写真に囲まれた環境に育ったのだろうが、彼自身に写真撮影や化学的処理の実体験がほとんどないのがその原因と思われる。
では、つっこみを少々。
1、「青い火花」で都電の花電車を撮るとき、祖父は自慢のライカでフラッシュを焚いている。このライカは1930年代の製品で板金作りの重たいものとこれ見よがしにあちこちで解説されているのだが、無改造のオリジナルならば、Ⅲaにシンクロ接点はない。
※数年前までスタジオでマグネシウムを音付きで焚いていた頭の固い祖父が、ライツ(商標の関係で今はライカカメラ。ライツのカメラゆえのライカだから、「机上の上」同様の間抜けな会社名)に純正改造を頼むだろうか?
2、「青い火花」で、ストロボと称して、一発で焼き切れるフラッシュを使用している。カーブを全速力で走ってくる花電車は、フラッシュの特性(FP球は発光時間がスピードライトよりかなり長い。幕速の遅い旧式フォーカルプレーンでは当たり前のこと)により、中ぶれした光の筋や帯になってしまい、絵にならない。
※フラッシュの特性を逆手にとって、花電車を「流し撮り」したのだと、鉄ヲタなら考えるかもしれないが、これも「絵葉書みたい」という感動の声があるから、矛盾する。スポーツの報道・芸術写真ならいざ知らず、画質のよいフィールドカメラで静止物を切り取るのが基本である絵葉書に、流し撮りなどありえない。
※「当時すでに骨董品扱いのライカとフラッシュを用い、驚異的なスピードで走る花電車を、たった1ショットでみごとに切り取った」というドラマを創ったつもりなのだろうが、写真を少しかじっていれば「ありえない虚構」とすぐに分かる。「絵葉書」と「一発で焼き切れるフラッシュ」を使わなければ、この話は破綻していなかった。
※ちなみに、題の「青い火花」という伏線により、2台のフラッシュとパンタグラフの青い火花が神様からのクリスマスプレゼントとしてシンクロしたという「夢のような仮説」も存在するのだが、これとてフォーカルプレーン(フラッシュを想定したFP接点はシャッター幕が全開していない状態で作動)のせいで見事に破綻している。
3、「青い火花」で、祖父による順ちゃんの写真が失敗作だったとき、僕が暗室を開けてしまったせいで撮り直しという芝居をするが、同時に父のフィルムを感光させてしまうという笑い話がある。直前に暗室内で赤いランプを使っているので、モノクロの印画紙を焼き付け中の事故ということになっているが、例えモノクロでも、赤い光の下でフィルム現像はできない。
※プロが例え完全暗室を持っていても、フィルム用の現像タンクがなぜ必須かを考えれば自ずと答が出る。筆者がフィルム現像をしたことがない、あるいは全工程を見たことがないのは明白。
4、「青い火花」や「遺影」では、乾板(おそらく4x5inchかそれ以上のサイズのカットフィルムのこと)で肖像写真を撮っていた祖父が、最後の「卒業写真」ではライカだけを使っている。昭和40年代には、一般家庭にあまねく35mmカメラが普及しているから、乾板や120判ロールフィルムが使える中・大判カメラ(一般にビューやテクニカルと呼ばれる種類)や、ローライ(おそらく伝統的な二眼レフ・ローライコードかフレックス)は写真館において必須であるし、この作品にもそれらしき記述がある。素人ならいざ知らず、職業写真家がレンジファインダー式35mmカメラの縦位置でポートレートを撮るなんていう愚の骨頂を、1969年にやったとは思えない。ましてや、いつも首に掛けてあるライカには、ボケ味を楽しもうにも楽しめないエルマーがねじ込んであったはず。
※ボケが進行中の祖父は、もうライカしか使えなかったという「落ち」なのだとは思う。ライカでポートレート撮影は可能だが、レンズは90mmぐらいに換えるべきだし、バルナックライカゆえ、アクセサリシューにファインダーを追加する必要あり。そんな記述はまったくない。
※ちまたで大流行の自撮り写真が、なぜ不細工になるかが分かっている人は、少しでも写真を勉強したことがある人。画角が広いレンズで近寄れば、当然デフォルメが起こるので、顔のアップを撮ると、鼻が大きく耳が小さな写真になる。それを防ぐため、プロは長焦点レンズを多用し、離れた所から上半身像を撮るのだ。もちろん、自撮りでも、分かっている人は鏡に映った自分を撮影し、デフォルメを防いでいる例も散見する。逆に、建物内などの奥行きが狭いところで撮る集合写真では、デブは真ん中に位置していないと、より太って写ってしまう。さてさて、最後の問題は理解できたかな。両端に並ぶのはタブーよ。そこの奥様!
5、父の最新型のペンタックスがやたらほめちぎられる。1969年時点のペンタックスは安くて便利な一般カメラであって、プロがこれ一台と決めて使うカメラではなかった。この時期の一眼レフの世界一はNikonFだから、浅田家にペンタックスが一台あったに一票。ましてや、最新のSPならば絞り込みのTTL測光を内蔵しているので、最先端のスポットメータか伝統的な入射光式でもない限り、父が風景写真に常用している露出計は無用の長物。ただし、ポートレートが目的ならばセレンを用いた入射光式のそれは祖父が珍しく思うような機器ではなく、プロなら必須の道具で、露出計の記述についても矛盾。
※ペンタックスは、文中では安直な最新カメラというような、現在なら、「押すだけ」のコンデジや、カメラの歴史や言葉の意味を知らない人が考えついたに相違ない名称「ミラーレス一眼」にあたる扱いを受けている。ペンタックスの名誉のために書き添えると、SPは露出計が絞り込み測光のマニュアル操作なので、押すだけでは撮れないし、フォーカスも手動。電池が切れてもSLだと思えば使えた。要は、モノクロフィルムで、「今日なら、1/125秒のF8」と光が読める人なら、ライカもペンタックスもマニュアル機としての操作は同じ。
※「ペンタックスの名誉」なんて言葉を使ってしまったので、実はペンタックスにもプロユースのカメラがあったことを付記しておく。67だ。簡単に言えば、巨大な一眼レフ。ガンマニアなら、S&W M29(ご存知ダーティハリーの愛用銃)だと思えばよい。昭和初期のライカとは違い、たいした値段ではなかったから、その気さえあれば誰にでも買えた代物(僕の友人が持っていた)。しかし、片手ではホールドできない重さと、ショックがあるので、マニア以外の素人が手を出すことはない。ただ、このカメラがプロに存在価値を認められた頃には、霞町付近を走る都電は姿を消していたから、時代考証の点で難あり。また、父は首(普通は首と肩となんだけど……orz)から2台のペンタックスを提げていたそうだから、物理的にも無理。
6、「青い火花」のラストは、祖父の遺骨に供えた愛用のカメラ。「ライカの焦点は∞(無限大)の印に合わされていた。」でしめくくられるが、それが当たり前。
※永遠のカメラマンという洒落のつもりなのだろうが、単純で稚拙。沈胴は別扱いとして、レンズを∞マークに合わせることと、レンズを最小サイズにすることは同義。カメラの携行や保管時にそうするのは当たり前のこと。かさばっていると、どこかで打ち傷を作り、最悪の場合は光軸が狂うから。
[おまけ]
仮に、『霞町物語』が映画化されるならば、明子(はるこ)は吉高由里子で決まり。彼女以外には考えられない。5年以内に実現すれば、映画館に足を運ぶよ……orz。
※2019/05/19
Webで見つけた「夢のような仮説」に対する反証と、6(∞)を追加。

再再度、読了。
1951年生まれの作者の青春時代が反映された作品。実体験にしろ、聞きかじりであったにしろ、生粋の江戸っ子で、ある程度お金持ちでなければその存在さえ知らないことも多々。勉強になりますた……orz。
さすがは、直木賞作家。「すばらしい言い回し!」「かっこいい伏線!」と、うめいたことが多々。
印象に残ったことばを少々、
「霞町物語」……「ごきげんよう」・孔雀の羽のいろをしたドレス
「夕暮れ隧道」……波間に漂うクラゲのようになった女・「そっくりね、今日の私たち」
「青い火花」……「おめえは、やさしさが足んねえ。」・幸福な子供
「雛の花」……セピア色・「おおなりこま」
「卒業写真」……スチール写真・幸福な子供
反面、カメラや写真に関しては、「これ、きっと勘違い」と時代考証してみたり、「それって、ど素人の考え」と毒ついてみたり。
浅田次郎の実家は、写真機材の卸商だったとかカメラ屋だったとかいうWebデータが実在するところから、カメラや写真に囲まれた環境に育ったのだろうが、彼自身に写真撮影や化学的処理の実体験がほとんどないのがその原因と思われる。
では、つっこみを少々。
1、「青い火花」で都電の花電車を撮るとき、祖父は自慢のライカでフラッシュを焚いている。このライカは1930年代の製品で板金作りの重たいものとこれ見よがしにあちこちで解説されているのだが、無改造のオリジナルならば、Ⅲaにシンクロ接点はない。
※数年前までスタジオでマグネシウムを音付きで焚いていた頭の固い祖父が、ライツ(商標の関係で今はライカカメラ。ライツのカメラゆえのライカだから、「机上の上」同様の間抜けな会社名)に純正改造を頼むだろうか?
2、「青い火花」で、ストロボと称して、一発で焼き切れるフラッシュを使用している。カーブを全速力で走ってくる花電車は、フラッシュの特性(FP球は発光時間がスピードライトよりかなり長い。幕速の遅い旧式フォーカルプレーンでは当たり前のこと)により、中ぶれした光の筋や帯になってしまい、絵にならない。
※フラッシュの特性を逆手にとって、花電車を「流し撮り」したのだと、鉄ヲタなら考えるかもしれないが、これも「絵葉書みたい」という感動の声があるから、矛盾する。スポーツの報道・芸術写真ならいざ知らず、画質のよいフィールドカメラで静止物を切り取るのが基本である絵葉書に、流し撮りなどありえない。
※「当時すでに骨董品扱いのライカとフラッシュを用い、驚異的なスピードで走る花電車を、たった1ショットでみごとに切り取った」というドラマを創ったつもりなのだろうが、写真を少しかじっていれば「ありえない虚構」とすぐに分かる。「絵葉書」と「一発で焼き切れるフラッシュ」を使わなければ、この話は破綻していなかった。
※ちなみに、題の「青い火花」という伏線により、2台のフラッシュとパンタグラフの青い火花が神様からのクリスマスプレゼントとしてシンクロしたという「夢のような仮説」も存在するのだが、これとてフォーカルプレーン(フラッシュを想定したFP接点はシャッター幕が全開していない状態で作動)のせいで見事に破綻している。
3、「青い火花」で、祖父による順ちゃんの写真が失敗作だったとき、僕が暗室を開けてしまったせいで撮り直しという芝居をするが、同時に父のフィルムを感光させてしまうという笑い話がある。直前に暗室内で赤いランプを使っているので、モノクロの印画紙を焼き付け中の事故ということになっているが、例えモノクロでも、赤い光の下でフィルム現像はできない。
※プロが例え完全暗室を持っていても、フィルム用の現像タンクがなぜ必須かを考えれば自ずと答が出る。筆者がフィルム現像をしたことがない、あるいは全工程を見たことがないのは明白。
4、「青い火花」や「遺影」では、乾板(おそらく4x5inchかそれ以上のサイズのカットフィルムのこと)で肖像写真を撮っていた祖父が、最後の「卒業写真」ではライカだけを使っている。昭和40年代には、一般家庭にあまねく35mmカメラが普及しているから、乾板や120判ロールフィルムが使える中・大判カメラ(一般にビューやテクニカルと呼ばれる種類)や、ローライ(おそらく伝統的な二眼レフ・ローライコードかフレックス)は写真館において必須であるし、この作品にもそれらしき記述がある。素人ならいざ知らず、職業写真家がレンジファインダー式35mmカメラの縦位置でポートレートを撮るなんていう愚の骨頂を、1969年にやったとは思えない。ましてや、いつも首に掛けてあるライカには、ボケ味を楽しもうにも楽しめないエルマーがねじ込んであったはず。
※ボケが進行中の祖父は、もうライカしか使えなかったという「落ち」なのだとは思う。ライカでポートレート撮影は可能だが、レンズは90mmぐらいに換えるべきだし、バルナックライカゆえ、アクセサリシューにファインダーを追加する必要あり。そんな記述はまったくない。
※ちまたで大流行の自撮り写真が、なぜ不細工になるかが分かっている人は、少しでも写真を勉強したことがある人。画角が広いレンズで近寄れば、当然デフォルメが起こるので、顔のアップを撮ると、鼻が大きく耳が小さな写真になる。それを防ぐため、プロは長焦点レンズを多用し、離れた所から上半身像を撮るのだ。もちろん、自撮りでも、分かっている人は鏡に映った自分を撮影し、デフォルメを防いでいる例も散見する。逆に、建物内などの奥行きが狭いところで撮る集合写真では、デブは真ん中に位置していないと、より太って写ってしまう。さてさて、最後の問題は理解できたかな。両端に並ぶのはタブーよ。そこの奥様!
5、父の最新型のペンタックスがやたらほめちぎられる。1969年時点のペンタックスは安くて便利な一般カメラであって、プロがこれ一台と決めて使うカメラではなかった。この時期の一眼レフの世界一はNikonFだから、浅田家にペンタックスが一台あったに一票。ましてや、最新のSPならば絞り込みのTTL測光を内蔵しているので、最先端のスポットメータか伝統的な入射光式でもない限り、父が風景写真に常用している露出計は無用の長物。ただし、ポートレートが目的ならばセレンを用いた入射光式のそれは祖父が珍しく思うような機器ではなく、プロなら必須の道具で、露出計の記述についても矛盾。
※ペンタックスは、文中では安直な最新カメラというような、現在なら、「押すだけ」のコンデジや、カメラの歴史や言葉の意味を知らない人が考えついたに相違ない名称「ミラーレス一眼」にあたる扱いを受けている。ペンタックスの名誉のために書き添えると、SPは露出計が絞り込み測光のマニュアル操作なので、押すだけでは撮れないし、フォーカスも手動。電池が切れてもSLだと思えば使えた。要は、モノクロフィルムで、「今日なら、1/125秒のF8」と光が読める人なら、ライカもペンタックスもマニュアル機としての操作は同じ。
※「ペンタックスの名誉」なんて言葉を使ってしまったので、実はペンタックスにもプロユースのカメラがあったことを付記しておく。67だ。簡単に言えば、巨大な一眼レフ。ガンマニアなら、S&W M29(ご存知ダーティハリーの愛用銃)だと思えばよい。昭和初期のライカとは違い、たいした値段ではなかったから、その気さえあれば誰にでも買えた代物(僕の友人が持っていた)。しかし、片手ではホールドできない重さと、ショックがあるので、マニア以外の素人が手を出すことはない。ただ、このカメラがプロに存在価値を認められた頃には、霞町付近を走る都電は姿を消していたから、時代考証の点で難あり。また、父は首(普通は首と肩となんだけど……orz)から2台のペンタックスを提げていたそうだから、物理的にも無理。
6、「青い火花」のラストは、祖父の遺骨に供えた愛用のカメラ。「ライカの焦点は∞(無限大)の印に合わされていた。」でしめくくられるが、それが当たり前。
※永遠のカメラマンという洒落のつもりなのだろうが、単純で稚拙。沈胴は別扱いとして、レンズを∞マークに合わせることと、レンズを最小サイズにすることは同義。カメラの携行や保管時にそうするのは当たり前のこと。かさばっていると、どこかで打ち傷を作り、最悪の場合は光軸が狂うから。
[おまけ]
仮に、『霞町物語』が映画化されるならば、明子(はるこ)は吉高由里子で決まり。彼女以外には考えられない。5年以内に実現すれば、映画館に足を運ぶよ……orz。
※2019/05/19
Webで見つけた「夢のような仮説」に対する反証と、6(∞)を追加。
2013年11月04日
モノクロのフィルム現像
おっさんたちしか知らない荒技
大量に135フィルムを撮影してしまったとき、4本用タンクがあれば便利でいい。ところが、もう4本用タンクはなかなか入手できない。
そういうときは、かつてプロから教えてもらった「必殺の方法」。
35mmフィルムを背合わせして、リールに2本同時に巻き込む。フィルムは乳剤面を内側にして反るので、完全暗室やダークバッグ内でも問題なく裏表が判別可能。自信がなければ、明るい所で先端だけセロテープで合体させておけばよい。
Nikor純正品しか使っていなかったので、今でも入手可能なLPL版で可能かどうかは定かではないが……。
もちろん、1本巻くのに四苦八苦しているような不器用な人には無理な話。
大量に135フィルムを撮影してしまったとき、4本用タンクがあれば便利でいい。ところが、もう4本用タンクはなかなか入手できない。
そういうときは、かつてプロから教えてもらった「必殺の方法」。
35mmフィルムを背合わせして、リールに2本同時に巻き込む。フィルムは乳剤面を内側にして反るので、完全暗室やダークバッグ内でも問題なく裏表が判別可能。自信がなければ、明るい所で先端だけセロテープで合体させておけばよい。
Nikor純正品しか使っていなかったので、今でも入手可能なLPL版で可能かどうかは定かではないが……。
もちろん、1本巻くのに四苦八苦しているような不器用な人には無理な話。
2013年01月02日
カメラの発掘……2013/01/02
帰省ついでに、昔の僕の部屋へ上がってみたら、父の写真が大量に保存されていた。花の写真が大半で、すべてが台紙に貼られており、整理がきちんとできていた。
僕と妹がかつて使っていた二段ベッドに、カメラバッグが大量に積まれていたので、少々開いてみた。
ところが、途中から電池抜きモードになり、それはそれは大変だった。要するに、カメラや付属品に装填された電池が寿命により液漏れし、それが原因で機器を不良品や廃品に変貌させていた。ストロボ(スピードライト)の類は、そのほとんどが液漏れによって電池ボックスが腐っていた。カメラ本体の2CR-5Wなどは、案外頑強で、なんとか救えるものもあった。
参考までに、ストロボのケース内に予備として保管されていた新品アルカリ電池の死体。漏れた電解液によってパッケージが中から破られているのが見物。

さて、カメラの方は、最初に出てきたのがMAKINA67。実は、大学の卒業アルバムの写真を、このカメラで撮った。ただし、僕はそのアルバムを持っていない。次にW67が出てきたので、ペアで記念写真。値段はたいしたことないが、知る人ぞのみ知る逸品。

3番目に出てきたのは、ハッセルブラッド(Hasselblad 503CW)。本体には、ミラー・ファインダー・巻き取り機構ぐらいしか装備していないから、ボディよりも、カールツアイス製レンズの方が価値が高い。SWC(Hasselblad 903SWC)も同じケースから出てきたから、これもペアで記念撮影。500C/Mや、他にもレンズが多々どこかにあるはずだが、この2台だけでも100万……orz。

さて、次のはと手を伸ばすと、僕のバッグが置いてあった。若い頃、この手のバッグか、弾薬ケースをぶら下げて大学に通っていたが、カメラは鉄製で頑強な弾薬ケースに入れていたことがほとんど。

バッグを開いてみてびっくり。僕のカメラではなく、Leicaが出てきた。


実は、もうひとつの緑色のケースから出てきた2枚目の写真のレンズ3本の方が高い。おそらく、100万……orz。
僕なら、右側のElmarit-M・21mmが使いたいが、コレクターは左側のNoctilux-M・50mm・F1なんてレンズに触手が伸びるのだろう。開放で使わなければ存在価値がないレンズを、レンジファインダーで使うのは、本当の馬鹿だけだと思うけど……orz。
他にも、Fujiのパノラマカメラ?やCONTAXや、いろいろな交換レンズが出てきたが、前者をペアで撮影中に、「帰るぞお!」と下の階から呼ばれ、そそくさと階段を下りた。

最後の掃除として腐った電池を袋詰めしているときに、きれいな皮ケースのカメラを見つけたので、一台拾ってきて、自宅で開いてみた。
ローライ35の復刻版みたいだったが、全部銀色でびっくりした。軍艦部のアクセサリーシューがデザイン的に気に入らないのは、オリジナルを知っている「おじん」ならではかなあ?とうなだれたのは秘密。
きちんと動いたので、一度フィルムを入れてみたい。正式名はRollei35Classic。調べてみたら、1600台しか出荷されていない。もちろん、ローライも再度倒産した。

僕と妹がかつて使っていた二段ベッドに、カメラバッグが大量に積まれていたので、少々開いてみた。
ところが、途中から電池抜きモードになり、それはそれは大変だった。要するに、カメラや付属品に装填された電池が寿命により液漏れし、それが原因で機器を不良品や廃品に変貌させていた。ストロボ(スピードライト)の類は、そのほとんどが液漏れによって電池ボックスが腐っていた。カメラ本体の2CR-5Wなどは、案外頑強で、なんとか救えるものもあった。
参考までに、ストロボのケース内に予備として保管されていた新品アルカリ電池の死体。漏れた電解液によってパッケージが中から破られているのが見物。

さて、カメラの方は、最初に出てきたのがMAKINA67。実は、大学の卒業アルバムの写真を、このカメラで撮った。ただし、僕はそのアルバムを持っていない。次にW67が出てきたので、ペアで記念写真。値段はたいしたことないが、知る人ぞのみ知る逸品。

3番目に出てきたのは、ハッセルブラッド(Hasselblad 503CW)。本体には、ミラー・ファインダー・巻き取り機構ぐらいしか装備していないから、ボディよりも、カールツアイス製レンズの方が価値が高い。SWC(Hasselblad 903SWC)も同じケースから出てきたから、これもペアで記念撮影。500C/Mや、他にもレンズが多々どこかにあるはずだが、この2台だけでも100万……orz。

さて、次のはと手を伸ばすと、僕のバッグが置いてあった。若い頃、この手のバッグか、弾薬ケースをぶら下げて大学に通っていたが、カメラは鉄製で頑強な弾薬ケースに入れていたことがほとんど。

バッグを開いてみてびっくり。僕のカメラではなく、Leicaが出てきた。


実は、もうひとつの緑色のケースから出てきた2枚目の写真のレンズ3本の方が高い。おそらく、100万……orz。
僕なら、右側のElmarit-M・21mmが使いたいが、コレクターは左側のNoctilux-M・50mm・F1なんてレンズに触手が伸びるのだろう。開放で使わなければ存在価値がないレンズを、レンジファインダーで使うのは、本当の馬鹿だけだと思うけど……orz。
他にも、Fujiのパノラマカメラ?やCONTAXや、いろいろな交換レンズが出てきたが、前者をペアで撮影中に、「帰るぞお!」と下の階から呼ばれ、そそくさと階段を下りた。

最後の掃除として腐った電池を袋詰めしているときに、きれいな皮ケースのカメラを見つけたので、一台拾ってきて、自宅で開いてみた。
ローライ35の復刻版みたいだったが、全部銀色でびっくりした。軍艦部のアクセサリーシューがデザイン的に気に入らないのは、オリジナルを知っている「おじん」ならではかなあ?とうなだれたのは秘密。
きちんと動いたので、一度フィルムを入れてみたい。正式名はRollei35Classic。調べてみたら、1600台しか出荷されていない。もちろん、ローライも再度倒産した。

2009年05月31日
ブランドのこと……(2005/10/30)
日本で、クラウンと言えば、トヨタの高級車を思い出す。ただし、自動車は安くなっているから、今ではちんぴらでもクラウンに乗っている時代。あっ、ちんぴらはセル○オの方が多いんだっけ……すんまそんm(_ _)m。
土地や家屋が圧倒的に高い日本(僕はこれも吊り上げの一種だと思っている)だから、家すら持っていないのに高級車に乗っている輩も多々いる。一点豪華主義なのだろう。
閑話休題
NikonとNikomatやCanonとCanonetの違いはなんだろうか。
そう。クラウンとカローラの違いなのだ。NikonとCanonの名称が許されるのは、旧/日本光学の場合はNikonSシリーズ(距離計連動)とNikonFシリーズ(一眼レフ)だけ。旧/キヤノンカメラ(※現在もCanonはキヤノンでありキャノンではない)の場合は、Canonflexの流れを組む一眼レフと距離計連動カメラだけだった。
NikonやCanonと銘版に刻まれていれば、高価格と高品質の証。信頼性が圧倒的に高いのだから仕事に使えるカメラということになる。
ところが、いくらすばらしいカメラでも誰しも半年分の給料(※)をたかがカメラに突っ込めるわけではない。大多数を占める薄給の一般人をターゲットにしたカメラを企画した。
※父が1960年にNikonFを買ったとき、Fは彼の給料の約3か月分。彼はレンズも当時のフルセット(2.1cm・2.8cm・3.5cm・5cm・5.8cm・5.5cmMicro・10.5cm・13.5cm・13.5cmベローズ専用までは使ったことがあるから確実。すべて初期のcm版)で揃えた。当然のように、FP接点に繋ぐフラッシュから、フード、フィルター、ベローズ、接写リング、とどめに専用複写台(カメラ台にFしか固定できない仕様)まで、ほぼすべての純正品が揃っていた。おまけに、同時期にMamiyaFlexC2のフルセット(ボディ2台・65mm・80mm・105mm・135mm・180mm)も揃えているので、給料2年分以上をカメラに投じていると思う。母の情報によると亡き祖父の遺産を使い尽くしたとか……。今ならクラウンぐらいは買える。
そんな高級機と中級機の差別化のために生まれた名称が、Nikkorex・NikomatやCanonetだった。AsahiPentaxやMinoltaといった中級機メーカの製品と同等のカメラにはNikonやCanonの名称は使わなかったのだ。
ところが、Canonは早い時期に普及品にCanonの銘版を付け始めた。高級品としての名前さえ普及してしまえば、それを利用して安物を売りつけようという戦略である。
これは大当たりした。例えばCanonAE-1。どうしようもないおもちゃカメラだったが、一般には大受けした。困ったNikonは、事実上のNikomatをNikonEL2・NikonFM・NikonFEとして売り出した。しかし時すでに遅し。
ちなみに、僕のNikomatELには、Nikonの銘版が付いている。知らない人が見れば、NikonELだと勘違いしそう。個人による改造ではなく、Nikonが銘版を交換してくれた。Nikonブランドにこだわり続けたにしては、まぬけな話である。
Sonnarという名称がSonnarタイプではないレンズに冠されるのも、おそらくブランド名を利用して消費者の心をくすぐっているだけなのだろう。
土地や家屋が圧倒的に高い日本(僕はこれも吊り上げの一種だと思っている)だから、家すら持っていないのに高級車に乗っている輩も多々いる。一点豪華主義なのだろう。
閑話休題
NikonとNikomatやCanonとCanonetの違いはなんだろうか。
そう。クラウンとカローラの違いなのだ。NikonとCanonの名称が許されるのは、旧/日本光学の場合はNikonSシリーズ(距離計連動)とNikonFシリーズ(一眼レフ)だけ。旧/キヤノンカメラ(※現在もCanonはキヤノンでありキャノンではない)の場合は、Canonflexの流れを組む一眼レフと距離計連動カメラだけだった。
NikonやCanonと銘版に刻まれていれば、高価格と高品質の証。信頼性が圧倒的に高いのだから仕事に使えるカメラということになる。
ところが、いくらすばらしいカメラでも誰しも半年分の給料(※)をたかがカメラに突っ込めるわけではない。大多数を占める薄給の一般人をターゲットにしたカメラを企画した。
※父が1960年にNikonFを買ったとき、Fは彼の給料の約3か月分。彼はレンズも当時のフルセット(2.1cm・2.8cm・3.5cm・5cm・5.8cm・5.5cmMicro・10.5cm・13.5cm・13.5cmベローズ専用までは使ったことがあるから確実。すべて初期のcm版)で揃えた。当然のように、FP接点に繋ぐフラッシュから、フード、フィルター、ベローズ、接写リング、とどめに専用複写台(カメラ台にFしか固定できない仕様)まで、ほぼすべての純正品が揃っていた。おまけに、同時期にMamiyaFlexC2のフルセット(ボディ2台・65mm・80mm・105mm・135mm・180mm)も揃えているので、給料2年分以上をカメラに投じていると思う。母の情報によると亡き祖父の遺産を使い尽くしたとか……。今ならクラウンぐらいは買える。
そんな高級機と中級機の差別化のために生まれた名称が、Nikkorex・NikomatやCanonetだった。AsahiPentaxやMinoltaといった中級機メーカの製品と同等のカメラにはNikonやCanonの名称は使わなかったのだ。
ところが、Canonは早い時期に普及品にCanonの銘版を付け始めた。高級品としての名前さえ普及してしまえば、それを利用して安物を売りつけようという戦略である。
これは大当たりした。例えばCanonAE-1。どうしようもないおもちゃカメラだったが、一般には大受けした。困ったNikonは、事実上のNikomatをNikonEL2・NikonFM・NikonFEとして売り出した。しかし時すでに遅し。
ちなみに、僕のNikomatELには、Nikonの銘版が付いている。知らない人が見れば、NikonELだと勘違いしそう。個人による改造ではなく、Nikonが銘版を交換してくれた。Nikonブランドにこだわり続けたにしては、まぬけな話である。
Sonnarという名称がSonnarタイプではないレンズに冠されるのも、おそらくブランド名を利用して消費者の心をくすぐっているだけなのだろう。
2009年05月31日
DPE……(2006/01/07)
DPEとは、「Development Printing Enlargement」の略。
和製英語らしいが、DPE店を名乗っている店でも、本当のことを知らないことが多い。
Development
現像のこと……実は、フィルム現像のこと
Printing
焼き付けのこと……実は、ベタ焼き(なぜベタと呼ばれるのかは作業すれば分かる)のこと
Enlargement
引き伸ばしのこと……手札版相当(現在のL版)に焼かれること多い
だから、理屈上は、撮影済みフィルムを持って行って「現像お願いします」とDPE店に頼んでおけば、ネガができあがるわけだ。
だが、そんなことをしたら喧嘩になる。現像の意味が分かっていない人は、「現像」=「同時プリント」だと思っているからだ。言うまでもなく、感光体の処理工程である「現像」「停止」「定着」の「現像」とは無縁である。
もちろん、フィルム現像と共にベタ焼き処理なんかしたら、結果的に店が損をする。プリントと言っても、それはサービスサイズへの引き伸ばしを指しているからだ。ベタ焼きは、今のインデックスカードの原寸大版にあたる。
結局のところ、Printingにあたる「焼き付け」は、死語化した。
どこの家でも、本家(実家)には先祖の写真が残っているものだが、1960年代初期ぐらいまでの写真は、ベタ焼きが多い。
135フィルム(元は35mm映画フィルムの流用)を使うカメラが普及し、引き伸ばしが当たり前になるまでは、一般家庭では120フィルムが常用され、処理が最も安直なベタ焼きが最終プリント(60mm×60mmか60mm×45mm)として残されることが多かったのだ。稀に手札版以上の写真が残っていれば、十中八九それは写真館の作品。
写真マニアである父だが、父は自写像をほとんど残していないので、彼の若い頃の写真は、このベタ焼きが圧倒的に多い。
和製英語らしいが、DPE店を名乗っている店でも、本当のことを知らないことが多い。
Development
現像のこと……実は、フィルム現像のこと
Printing
焼き付けのこと……実は、ベタ焼き(なぜベタと呼ばれるのかは作業すれば分かる)のこと
Enlargement
引き伸ばしのこと……手札版相当(現在のL版)に焼かれること多い
だから、理屈上は、撮影済みフィルムを持って行って「現像お願いします」とDPE店に頼んでおけば、ネガができあがるわけだ。
だが、そんなことをしたら喧嘩になる。現像の意味が分かっていない人は、「現像」=「同時プリント」だと思っているからだ。言うまでもなく、感光体の処理工程である「現像」「停止」「定着」の「現像」とは無縁である。
もちろん、フィルム現像と共にベタ焼き処理なんかしたら、結果的に店が損をする。プリントと言っても、それはサービスサイズへの引き伸ばしを指しているからだ。ベタ焼きは、今のインデックスカードの原寸大版にあたる。
結局のところ、Printingにあたる「焼き付け」は、死語化した。
どこの家でも、本家(実家)には先祖の写真が残っているものだが、1960年代初期ぐらいまでの写真は、ベタ焼きが多い。
135フィルム(元は35mm映画フィルムの流用)を使うカメラが普及し、引き伸ばしが当たり前になるまでは、一般家庭では120フィルムが常用され、処理が最も安直なベタ焼きが最終プリント(60mm×60mmか60mm×45mm)として残されることが多かったのだ。稀に手札版以上の写真が残っていれば、十中八九それは写真館の作品。
写真マニアである父だが、父は自写像をほとんど残していないので、彼の若い頃の写真は、このベタ焼きが圧倒的に多い。
2009年05月31日
ブランド名……(2005/10/25)
Nicorのついでに、昔なつかしいスーパーベッサやビテッサをぐぐってみたら、日本語でも掛かるは掛かるは……。カメラコレクターは日本にも多数いるようだ。また、カメラにはそんな魅力があるような気がする。
銀塩カメラは終焉を迎えているのに、僕でも、ビテッサなら1台欲しい。\50000も出せば買えるのだから、元の値段を考えれば安い物だ。
ただ、Volgtlanderを、日本ではフォクトレンデルではなく、フォクトレンダーと呼ぶようになったことに違和感を感じる。Volgtlanderはフォクトレンデルだろ。昭和の時代のカタログには、みんなそう書いてあったし、僕の拙い独語力でもそうだ。
何を血迷ったか、コシナがVolgtlanderのブランドを買い取ったときに、フォクトレンダーときめうちしたようだ。本家となったコシナの命名ならしかたがない。
※2009/06/08付記
世界一強い国の母国語、米語こそが「世界の言語」だからしかたない……orz。
日本製カメラに駆逐されたContaxが京セラ(元Yashica)から、VolgtlanderやZeissIkonがコシナから発売されるのも何かの縁かもしれない。
京セラやコシナの名前では、だれも喜ばないのは事実だ。でも、かつて一世を風靡したブランド名を知っているお爺さんだけがこれらのカメラを買っているのだろうか。横文字がかっこいいという思いこみはないだろうか。
「観音カメラ」もまたいいぞ。もう一方の雄は、「日本のContax」だぞ。
ちなみに、チノンのように、Kodakと提携したのが仇になったのか、完全子会社化され、外資系企業によってブランド名が消されていく事例もある。
今月、僕がやっと手に入れたマザーボードは、Tyan製のTsunamiATだ。もちろん、「Tsunami」=「津波」なのは、言うまでもない。
日本語は、決して格好悪いわけではないのだ。
銀塩カメラは終焉を迎えているのに、僕でも、ビテッサなら1台欲しい。\50000も出せば買えるのだから、元の値段を考えれば安い物だ。
ただ、Volgtlanderを、日本ではフォクトレンデルではなく、フォクトレンダーと呼ぶようになったことに違和感を感じる。Volgtlanderはフォクトレンデルだろ。昭和の時代のカタログには、みんなそう書いてあったし、僕の拙い独語力でもそうだ。
何を血迷ったか、コシナがVolgtlanderのブランドを買い取ったときに、フォクトレンダーときめうちしたようだ。本家となったコシナの命名ならしかたがない。
※2009/06/08付記
世界一強い国の母国語、米語こそが「世界の言語」だからしかたない……orz。
日本製カメラに駆逐されたContaxが京セラ(元Yashica)から、VolgtlanderやZeissIkonがコシナから発売されるのも何かの縁かもしれない。
京セラやコシナの名前では、だれも喜ばないのは事実だ。でも、かつて一世を風靡したブランド名を知っているお爺さんだけがこれらのカメラを買っているのだろうか。横文字がかっこいいという思いこみはないだろうか。
「観音カメラ」もまたいいぞ。もう一方の雄は、「日本のContax」だぞ。
ちなみに、チノンのように、Kodakと提携したのが仇になったのか、完全子会社化され、外資系企業によってブランド名が消されていく事例もある。
今月、僕がやっと手に入れたマザーボードは、Tyan製のTsunamiATだ。もちろん、「Tsunami」=「津波」なのは、言うまでもない。
日本語は、決して格好悪いわけではないのだ。
2009年05月31日
フィルム現像……(2005/10/25)
モノクロフィルムの現像には、Nikor製ステンレスタンクを使っていた。
父の道楽のおかげで、我が家には、タンク・リールともに、135版が2本用・4本用、120版と各種揃っていた。その模倣品がLPLなどから販売され、今では意味も分からずナイコールタイプと呼ばれているらしい。元祖を知らぬ人の方が多い時代が来たわけだ。
Nikorオリジナルの設計はかなり優れていたから、おそらく特許か実用新案でおさえられていたはずだが、たった一つ欠点があった。
それは、フィルムを巻き始めるときのストッパ(フック)がないことだ。暗闇で先端を固定することが苦手な友人の中には、明るいところでそれを済ませるのもいた。
LPLが発売した模倣品は、その欠点を補うために、ステンレス製のストッパ(フック)がついていた。
先ほど、LPLのWebSiteで現物を確認してきたが、25年前の物と同様の品を、まだ製造していた。この分野も時間が止まっている世界だ。
件のタンクやリールは、すべて大学の部室に放置してきたので、もう手元にはない。
父の道楽のおかげで、我が家には、タンク・リールともに、135版が2本用・4本用、120版と各種揃っていた。その模倣品がLPLなどから販売され、今では意味も分からずナイコールタイプと呼ばれているらしい。元祖を知らぬ人の方が多い時代が来たわけだ。
Nikorオリジナルの設計はかなり優れていたから、おそらく特許か実用新案でおさえられていたはずだが、たった一つ欠点があった。
それは、フィルムを巻き始めるときのストッパ(フック)がないことだ。暗闇で先端を固定することが苦手な友人の中には、明るいところでそれを済ませるのもいた。
LPLが発売した模倣品は、その欠点を補うために、ステンレス製のストッパ(フック)がついていた。
先ほど、LPLのWebSiteで現物を確認してきたが、25年前の物と同様の品を、まだ製造していた。この分野も時間が止まっている世界だ。
件のタンクやリールは、すべて大学の部室に放置してきたので、もう手元にはない。
2009年05月31日
ダイレクトプリント……(2005/10/25)
一度だけ、フジクロームで撮影をしたことがある。カメラはOlympusのXA。妹が使い倒して、もう廃棄されたカメラだ。
旧友と日本海を旅行したとき、記念写真用にリバーサルフィルムを使ってみた。バイトで扱っていたダイレクトプリントの美しさが印象に残っていたからだ。
現像と同時にダイレクトプリントした。空の色が抜けるように青く、高価なフィルムと高価なプリントの価値を実感した。
今なら、フォトレタッチソフトで、「ちょちょいのちょい」の内容に感動していたのかもしれない。
当時でも、モノクロ写真なら、暗室でなんとでも料理できたのだ。
旧友と日本海を旅行したとき、記念写真用にリバーサルフィルムを使ってみた。バイトで扱っていたダイレクトプリントの美しさが印象に残っていたからだ。
現像と同時にダイレクトプリントした。空の色が抜けるように青く、高価なフィルムと高価なプリントの価値を実感した。
今なら、フォトレタッチソフトで、「ちょちょいのちょい」の内容に感動していたのかもしれない。
当時でも、モノクロ写真なら、暗室でなんとでも料理できたのだ。
2009年05月31日
Kodachrome……(2005/10/25)
実家の父の遺品を発掘すれば、退色したコダクローム(Kodachrome)が大量に出てくることと思う。
その中には、僕が1歳のときからのカラー写真が残っているはずだ。小さい頃、よく父がスライド上映をしてくれたから覚えている。
ただ、プリントは見た覚えがない。それもそのはず。昭和40年代(1965~74)は、ダイレクトプリントがまだ実用化される前だったせいだと思う。
発掘を急がねば、僕の幼少期のカラー写真は灰燼に帰してしまう。もちろん、モノクロ写真なら、想像を絶するほどの数が残存している。
コダクロームは、世界で最も歴史があり、おそらく世界で最も美しいリバーサルフィルムだ。なんと、「外式」だからKodak以外では現像できない。
実のところ、僕はカラー写真には興味がなかったので、100フィートで入手できるトライ-Xかネオパン400、たまにイルフォード製(名前は忘れた)しか常用していなかった。僕はフジクロームしか使ったことがないが、ダイレクトプリントしたものは残っている。
ちなみに、ダイレクトプリントはデジカメの写真を直接家庭用プリンタで出力することだと思っている香具師が多い。ダイレクトの意味はあっているけど、歴史が違う。
おまけに、「Kodachrome」(邦訳「ぼくのコダクローム」)は、PaulSimonの名曲だが、Nikonを手に入れて喜んでいるのがおもしろい。ぼくの写真もNikonFで撮影された。
最後に……。
この夏実家でデイロールを見つけた。100フィート巻のフィルムをパトローネに詰め込む例の道具だ。蓋を開けてみると、トライ-Xが出てきた。このフィルムは、約25年ぶりに日の目を見たことになる。ただし、フィルムだから日の目を見た時点でいっかんの終わり……orz。
その中には、僕が1歳のときからのカラー写真が残っているはずだ。小さい頃、よく父がスライド上映をしてくれたから覚えている。
ただ、プリントは見た覚えがない。それもそのはず。昭和40年代(1965~74)は、ダイレクトプリントがまだ実用化される前だったせいだと思う。
発掘を急がねば、僕の幼少期のカラー写真は灰燼に帰してしまう。もちろん、モノクロ写真なら、想像を絶するほどの数が残存している。
コダクロームは、世界で最も歴史があり、おそらく世界で最も美しいリバーサルフィルムだ。なんと、「外式」だからKodak以外では現像できない。
実のところ、僕はカラー写真には興味がなかったので、100フィートで入手できるトライ-Xかネオパン400、たまにイルフォード製(名前は忘れた)しか常用していなかった。僕はフジクロームしか使ったことがないが、ダイレクトプリントしたものは残っている。
ちなみに、ダイレクトプリントはデジカメの写真を直接家庭用プリンタで出力することだと思っている香具師が多い。ダイレクトの意味はあっているけど、歴史が違う。
おまけに、「Kodachrome」(邦訳「ぼくのコダクローム」)は、PaulSimonの名曲だが、Nikonを手に入れて喜んでいるのがおもしろい。ぼくの写真もNikonFで撮影された。
最後に……。
この夏実家でデイロールを見つけた。100フィート巻のフィルムをパトローネに詰め込む例の道具だ。蓋を開けてみると、トライ-Xが出てきた。このフィルムは、約25年ぶりに日の目を見たことになる。ただし、フィルムだから日の目を見た時点でいっかんの終わり……orz。